要約(100字): VORPはBPMを基に「代替可能選手(BPM -2.0)」との差を出場時間で累積する指標です。一方RAPMやEPMは、味方・相手の文脈を含め、在場による得失点影響を直接推定します。
前回の記事では、選手の「ボックススコア」を元にした主要指標、PER、Win Shares、BPMを解説しました。これらは選手が「何をしたか」を克明に記録する、強力なツールです。
(※未読の方は、まずこちらの基礎指標編から読むことをお勧めします)
しかし、真の分析は、その先にある問いに答えることで始まります。「そのプレーの結果として、チームは『何を得たのか』?」
この記事では、ボックススコアベースの累積指標の完成形であるVORPから、選手の「見えざる貢献」を可視化するプラスマイナス系の指標まで、NBA分析の最深部への旅を始めましょう。
見るポイント: ①VORP=“率(BPM)”を“量”へ積む ②RAPM/EPM=文脈(味方・相手・役割)込みの影響を見る
第1章:VORP – 選手の「総貢献量」を測る
VORP(Value Over Replacement Player)は、ボックススコアをベースにした累積指標の中で、最も洗練されたものの一つです。その核心は、「リプレイスメント・プレーヤー」という基準線との比較にあります。
1-1. VORPのエンジン「BPM」
VORPの計算の元となるのは、前回の記事でも紹介したBPM(Box Plus-Minus)です。BPMは、選手がコートにいる時間帯に、リーグの平均的な選手(BPM 0.0)と比較して100ポゼッションあたり何点分の貢献をしたかを推定する「率」の指標です。
1-2. 基準線としての「リプレイスメント・プレーヤー」
分析の世界では、選手の価値を測るための基準線として、BPMにして -2.0 に相当する選手を「リプレイスメント・プレーヤー」と定義しています。これは、10日間契約や最低保証年俸でいつでも獲得できるレベルの選手を指します。ここを“基準線”に足し引きするのがVORPです。[1]
1-3. 「率」から「量」へ
VORPは、BPM(率)に選手の出場時間を加味することで、シーズン全体でどれだけの価値を積み上げたかを示す「量」の指標に変換されます。
VORP の概念式
VORP = (BPM - (-2.0)) × (出場分 / チーム総分) × (チーム試合数 / 82)※ BPM(率)を出場時間で“量”へ変換します。[2]
1-4. VORPの限界:ウェストブルック問題
しかし、VORPの基盤であるBPMはボックススコアに依存するため、完璧ではありません。その限界を象徴したのが、ラッセル・ウェストブルックの2016-17シーズンです。当時のBPM 1.0では、彼の高いアシスト率と高いディフェンスリバウンド率の組み合わせが過大評価される形でスコアが膨張。この一件により、BPM 2.0で係数と正則化が見直されました。[3]
第2章:プラスマイナス革命 – 「真の影響力」を探る
ボックススコアが捉えきれない価値を測定するために生まれたのが、プラスマイナス系指標です。これは、選手がコートにいることでチームのパフォーマンスにどう影響したかを直接測定します。
2-1. 始まりの指標:Raw Plus-Minus (+/-)
選手がコート上にいる間のチームの得失点差を示す、シンプルな指標です。しかし、チームメイトや相手の質に大きく左右されるという致命的な欠陥があります。
2-2. 革命的指標:RAPM
Raw +/-の問題を統計学的に解決したのが、RAPM(Regularized Adjusted Plus-Minus)です。[4] これは、膨大なプレーデータを使い、他の全ての選手(チームメイトと相手)の影響を「調整」し、選手個人の純粋な影響力を算出します。ただし、単年のRAPMは誤差が大きく、複数年のデータや事前情報を用いることで安定化を図ります。
2-3. 現代の最先端指標:ハイブリッドアプローチ
RAPMは数シーズン分のデータが必要なため、単一シーズンの評価にはハイブリッドアプローチが用いられます。これは、ボックススコアモデルの安定性と、RAPMの厳密さを組み合わせたものです。
| 指標 | 何を入力にするか | 強み | 限界 | 向く場面 |
|---|---|---|---|---|
| VORP | BPM+出場時間 | シーズン“総量”で功績を把握 | 箱外の貢献は弱い | 年間総括・キャリア比較 |
| RAPM | オン/オフを正則化で連立推定 | 文脈込みの純粋影響 | 単年はノイズ多め | 守備/組合せ評価 |
| EPM | RAPM系+箱のハイブリッド | 予測力・解釈のバランス | モデル依存 | 単年の実力推定 |
| LEBRON | 箱+オン/オフ+役割補正 | 役割差や運要素を調整 | 外部仕様に依存 | スカウティング |
| RAPTOR | 箱+トラッキング+オン/オフ | 追跡データを反映 | 公開仕様が期で変遷 | ローテ設計 |
注:EPM[5], LEBRON[6], RAPTOR[7]などの指標は、仕様や公開状況が変わり得るため、最新の公式説明に依拠してください。
第3章:ケーススタディ – スタッツが語る「見えざる価値」
分析の核心は、選手が「何をしたか」(VORPなど)と、その「結果」(EPMなど)を突き合わせることにあります。
- 評価が割れやすいスコアラー:カーメロ・アンソニー
個人得点は大きい一方で、インパクト指標では評価が割れやすい時期がありました。高難度ミドルの比率や役割設計が、チーム効率に必ずしも直結しない局面があった可能性があります。 - ディフェンスの設計者:ドレイモンド・グリーン/アレックス・カルーソ
ボックススコアに出にくい守備の連携(X-out(ヘルプローテの入れ替わり)の初動、スクリーンナビゲート等)が、RAPMやEPMに反映されやすい選手像です。 - 見えざるエンジン:スティーブン・アダムズ
強力なスクリーンやオフェンスリバウンドで、在場時のチームオフェンスが上向く傾向が見られます。得点以外の“期待値の底上げ”が価値の源泉です。
明日の観戦で使うなら(3点)
- VORPで長期の“総貢献”をつかむ(シーズンやキャリアの厚み)。
- RAPM/EPMで組み合わせと相手込みの“いまの強さ”を見る。
- 乖離は赤信号:VORP↑×EPM↓(または逆)なら、役割・ラインナップ・サンプルを確認。
結論:指標は「答え」ではなく、「問い」をくれる
どの単一の指標も万能ではありません。VORPのようなボックススコア指標は選手の「総生産量」を、EPMのようなインパクト指標はその生産性が勝利に結びついているかの「真偽判定機」として機能します。
両者の評価が高い選手(ヨキッチ、レブロンなど)は、そのスタッツが勝利に直結していることが確認できます。逆に、両者の評価が大きく乖離する選手は、より深い調査を促す「赤信号」となります。
発展的分析の真の目的は、絶対的な答えを出すことではなく、我々がより知的な探究を続けるための武器を授けることです。ボックススコアが語る「何が起きたか」と、インパクト指標が明らかにする「その結果どうなったか」を突き合わせることで初めて、我々は選手の真の価値に迫ることができるのです。
次に読む:
基礎指標編(PER/WS/BPM)
出典(脚注)
- Basketball-Reference:VORP定義(-2.0基準/82換算)
- Basketball-Reference:About BPM(BPMは率、VORPは量)
- RAPM 概説(APM→RAPM、正則化の意義)
- DunksAndThrees:EPM の説明
- BBall-Index:LEBRON の説明
- RAPTOR の仕様説明(FiveThirtyEight)
更新履歴
– 2025-09-20:最終レビューを反映。冒頭要約・比較表・脚注リンクを追記/ケーススタディの表現を中立化

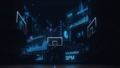

コメント